居宅保育って聞いたことあるけど、実際どうなの?
利用した人の体験談が知りたい!
毎日家に他人が来るって、正直どうなんだろう…?
保活を進める中で 「居宅保育」という選択肢を知ったものの、
- やっぱり普通の保育園のほうが安心だよね
- 居宅保育って実態がよく分からないし不安…
と、具体的な情報がないまま候補から外してしまっていませんか?
選択肢を狭めることで、待機児童になり、あとから後悔する可能性があります。
実際に、我が家も第1子の保活で「認可保育園に全オチ」という経験をしました。
すでに復職が決まっていたため、何が何でも保育園を確保しなければならず、焦りと不安でいっぱいに…。
「もっと早く、広い選択肢を持っておけばよかった…」 と痛感した出来事でした。
その反省を活かし、第2子のときは産後2ヶ月という早期復職にあたり、居宅保育を第一希望に設定。
生後2ヶ月から生後8ヶ月までの半年間、実際に居宅保育にお世話になりました。
実際に使ってみたところ、想像以上に安心でき、メリットも多いサービスでした!
この記事では、
- 居宅保育は実際どんなサービスなのか?
- 居宅保育のメリットやデメリットは?
- 保育士さんが家に来るって実際どうだった?
といった、実体験をふまえたリアルな情報を詳しくお伝えします。
居宅保育が気になっている方はもちろん、保育園の選択肢を増やして後悔のない保活をしたい方はぜひ最後までお読みください。
この記事を書いた人

居宅保育とは
保育内容は認可保育園と同様に「保育所保育指針」に沿った内容です。
保育園の先生が自宅で保育をしてくれるというイメージをして頂くと分かりやすいかと思います。
居宅保育のメリットとデメリット一覧
我が家が半年間利用して感じたメリットとデメリットを紹介します。
我が家は夫婦ともにフル在宅ワークでの居宅保育利用でリビングを保育室にしていました
| メリット | デメリット |
|---|---|
| マンツーマンでしっかり保育してもらえる | お昼ご飯の準備でリビングに行くのが気まずい |
| 我が子の成長に合わせた遊びをしてくれる | 昼寝中にリビングに行くのが気まずい |
| 毎日のように児童館やお散歩に連れていってもらえる | レンチン以外の調理をしてもらえない |
| 保育者が保育中の写真を見せてくれるのでどんな時間を過ごしたか分かる | 間取りによっては保育室にいると子どもや先生の声がうるさく感じる場合もある |
| 制作が頻繁にある | 親参加の行事がない |
| 送り迎えが不要 | |
| 持ち物に名前を書く手間がかからない | |
| 集団生活じゃないので感染症にかかる可能性が低い |
居宅保育を利用しての感想
「もう一人のママ」がいるような安心感
居宅保育を利用して感じたのは、「自分以外にもママがいる」ような感覚でした。
担当してくれる保育者は 2〜3名に絞られ、毎日ローテンションで1人が来て、子どもに対してマンツーマンでしっかり寄り添って保育してくれます。
保育園の先生がクラス全体を見守るのに対し、居宅保育では「我が子だけの先生」 がいる状態。
そのため、本当に細かい成長まで見逃さず、時には親よりも小さな変化に気づいてくれることも。
育児の悩みも「親目線」で相談できる安心感
例えば、離乳食の進め方や寝かしつけの方法。
日々マンツーマンで見守ってくれているからこそ、「親とほぼ同じ視点」 で相談に乗ってもらえたことが印象的でした。
保育園では、先生方は大勢の子どもを一度に見守るため、どうしても一人ひとりの細かい変化に気づくのが難しいのが実情。
そのため、私は 保育園の先生には細かい成長や育児の相談をすることは少なかったですが、居宅保育の保育者の方にはまさに「二人三脚」で子育てをしてもらったと感じています。
マンツーマンだからこそ感じられる「先生の愛」
居宅保育では、先生方の愛情がひしひしと伝わってくる瞬間がたくさんありました。
例えば、
- 数日ぶりの再会でも、「○○ちゃん、会いたかった~!」 と笑顔で迎えてくれる
- 「あれ?私じゃなくて先生が産んだんだったかな?」 と思うくらい愛情たっぷりに接してくれる
この温かい関わりが、安心感や信頼感に繋がり、心から子どもを託すことができました。
居宅保育だからこそ体験できた、貴重な時間
保育時間中には、
- 成長に合わせた手作りおもちゃや制作遊び
- 自宅や近隣での児童館の行事参加
- 手先を使ったさまざまなアクティビティ
など、もし私が育休中にマンツーマンで子どもと過ごしていたらここまでたくさんの経験をさせることは難しかっただろうなと思うほど、充実した時間を過ごさせてもらいました。
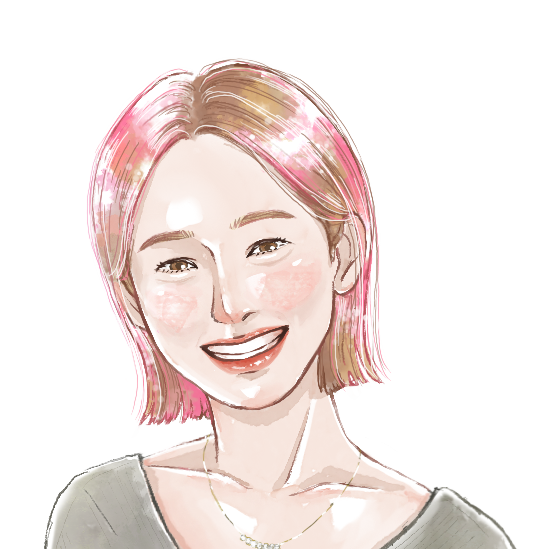
子どもにとっても、親にとっても、こんなにありがたい保育の形があるんだと実感できる、貴重な経験でした。
居宅保育に対する考え方は家庭それぞれ
家の中に家族以外の人がいるって、どうなんだろう?居宅保育を検討する際、こんな疑問を持つ方も多いかもしれません。
家庭ごとに異なる「居宅保育への感じ方」
ママ友と話した感じだと以下のような傾向がある気がしました。
| 住居 | 説明 | |
|---|---|---|
| 戸建ての場合 | 普段、家に他人が入る機会が少ないため、「家の中に家族以外の人がいる」ことに違和感を持つ可能性が高い | |
| 集合住宅の場合 | 日常的に家族以外の人と建物内で顔を合わせることが多く、心理的ハードルが低いかもしれない | |
我が家の場合:マンション暮らし+オープンな感覚が後押し
我が家は マンション住まい で、もともと比較的オープンな感覚でした。さらに、友人が頻繁に遊びに来る環境だったこともあり、「家族以外の人が家の中にいること」が特別なことではありませんでした。
たまたま夫婦ともにほぼ在宅ワークでしたが、もし出社勤務だったとしても、居宅保育を利用することに抵抗はなかったと思います。
実際に利用してみての安心感
言わずもがなですが、依頼してる期間に家から物がなくなるなどどいうことはもちろんありませんでした。
夫婦ともに出社などで家を空けて居宅保育をお願いしている時間も何度もありましたが、不安に感じることは無かったです。
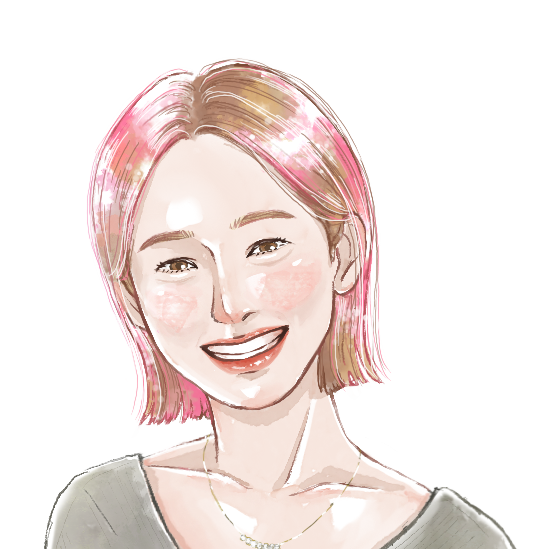
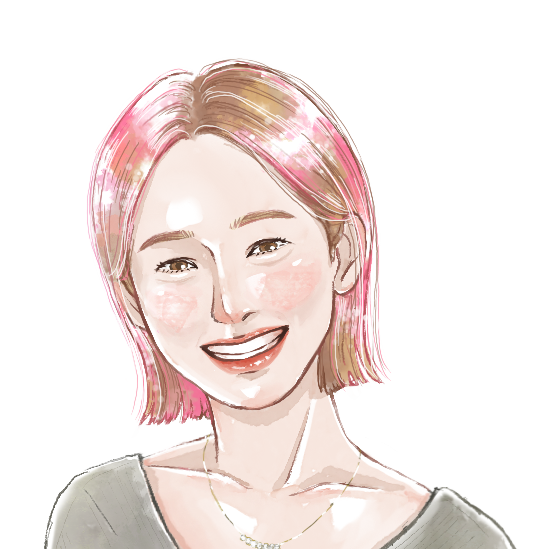
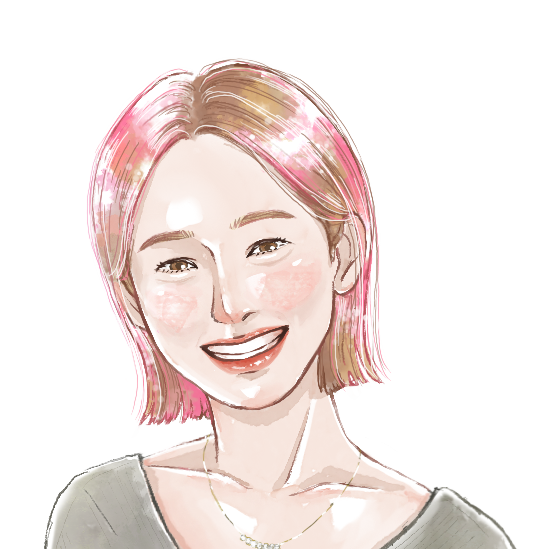
むしろ「毎日来客がある状態」と思えば、家をキレイに保つモチベーションに(笑)
プライバシーの考え方や感覚は家庭それぞれ
「他人を家に入れることに抵抗がある」 という家庭も、もちろんあると思います。そうした場合は、無理に利用する必要はありません。
居宅保育が向いているかどうかは、家庭の価値観やライフスタイル次第
大切なのは、無理のない範囲で納得できる選択をすること
居宅保育(ある日の1日)
| 時間 | 出来事 |
|---|---|
| 9:50 | 保育者来訪 |
| 10:00 | おむつ替え(大) |
| 10:20~10:35 | お昼寝(15分) |
| 10:40~12:00 | お散歩・児童館で遊ぶ |
| 12:10 | ミルク(180ml) |
| 12:30 | おむつ替え(小) |
| 12:45~15:05 | お昼寝(2時間20分) |
| 15:10 | おむつ替え(小) |
| 15:35 | ミルク(180mil) |
| 16:00~17:00 | 近所の公園などをお散歩 |
| 17:00 | おむつ替え(小) |
| 17:00~17:50 | 室内遊び |
| 17:50 | こども引き取り |
居宅保育でのシーズンイベント
我が家は 10月〜翌年3月末までの半年間 居宅保育を利用しましたが、その間もさまざまな季節のイベントを楽しませてもらいました。
| イベント | 説明 | |
|---|---|---|
| クリスマス | サンタとトナカイの制作、児童館でフォト撮影 | |
| お正月 | 児童館のお正月イベントで獅子舞の舞を見物 | |
| 節分 | 児童館で鬼のお面づくり | |
| ひなまつり | 児童館でおひなさまの制作 | |
| 遠足 | 他の居宅保育を利用しているお友達と一緒に遊び場へお出かけ | |
児童館イベントへの積極的な参加
季節のイベント時には、児童館で開催されるイベントに参加することが多かったです。
特にありがたかったのは、先生方が児童館のイベントスケジュールを調べて、積極的に参加させてくれたこと!
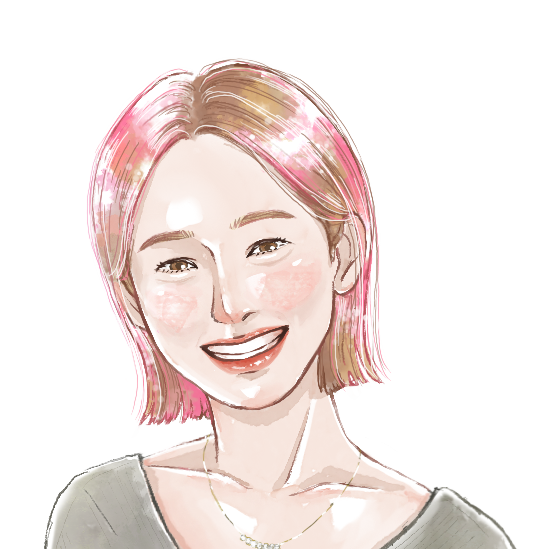
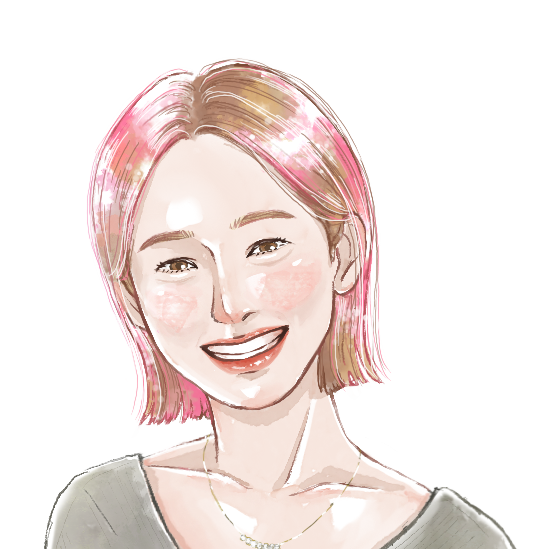
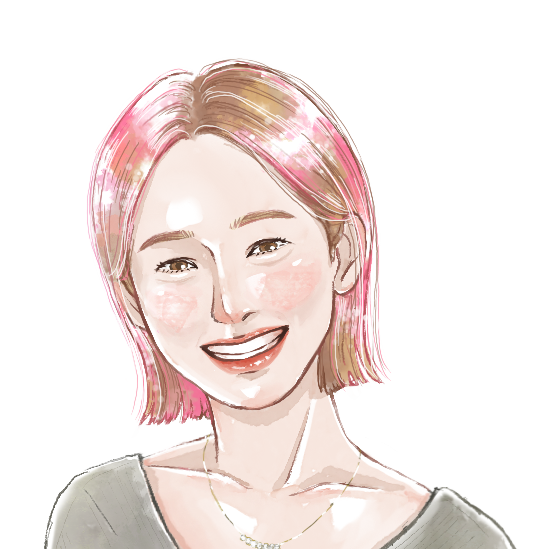
私自身が育休中でマンツーマン育児だったら、ここまでこまめにイベントに参加するのは難しかっただろうな と思います
遠足まで実施!貴重な経験に
さらに、居宅保育では 「遠足」まで実施!同じく居宅保育を利用しているお友達と一緒に保育者と電車に乗ってお出かけしました。
居宅保育でも、充実したシーズンイベントを楽しめた!
半年間という短い期間でしたが、ただ預けるだけでなく、季節の行事やイベントを通じて、さまざまな体験をさせてもらえたことに感謝しています。
「家で保育してもらう」というイメージの強い居宅保育ですが、実際には児童館やお出かけの機会も多く、外の世界との関わりもたっぷり持たせてもらえました。
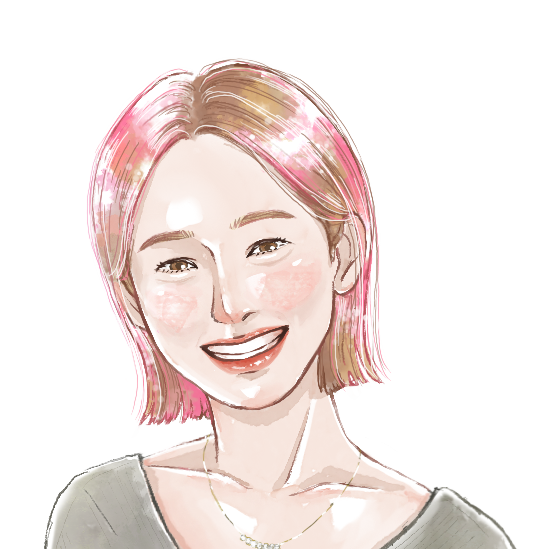
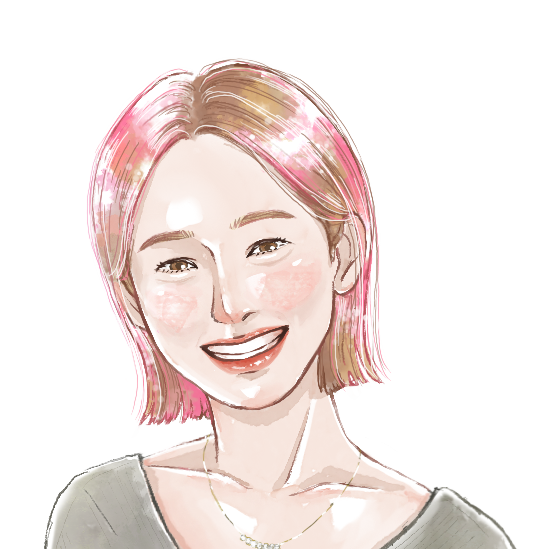
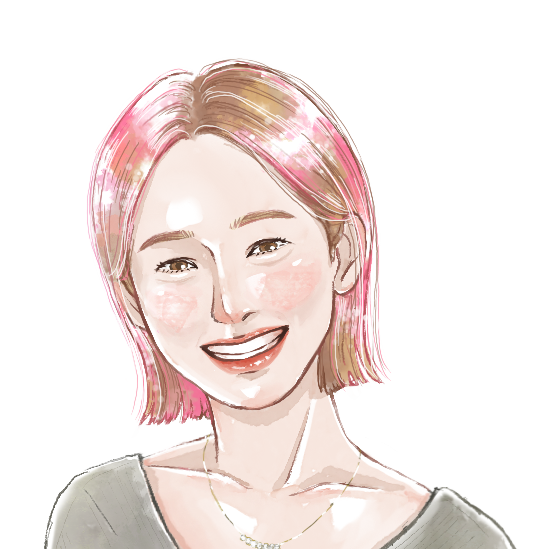
子どもにとっても親にとっても、かけがえのない時間になったと感じています
居宅保育に慣れるまでは泣くけれど、その先に変化が
最初は、やっぱり泣く…
最初の頃は、もちろん泣きます。知らない人が家にやってきて、抱き上げられ、親と引き離されるのですから、それはもう泣きますよね。
でも、これは 保育園の慣らし保育と同じで、新しい環境に適応するまでのプロセス。慣れるまでは泣いてしまうのは当然のことでした。
慣れたら、先生の訪問を喜ぶように!
慣れてからも、担当以外の保育者が来ると人見知りをして半分くらい泣いている日も(笑)。でも、慣れた先生が来ると、朝から嬉しそうに!
先生が到着すると、まずは洗面所で手を洗い、エプロンなどの準備をしてからリビングへ。それを待ちきれないかのように、「早く!」と言わんばかりの表情で、先生の訪問を心から歓迎していました!
親が近くにいても、保育者としっかり遊んでいた
我が家の場合、生後2ヶ月という「まだ何も分からない時期」から預けていたこともあり、保育時間中に親が昼食の準備などでリビングにいても、「ママ(パパ)のところに行きたい!」と泣くことはありませんでした。
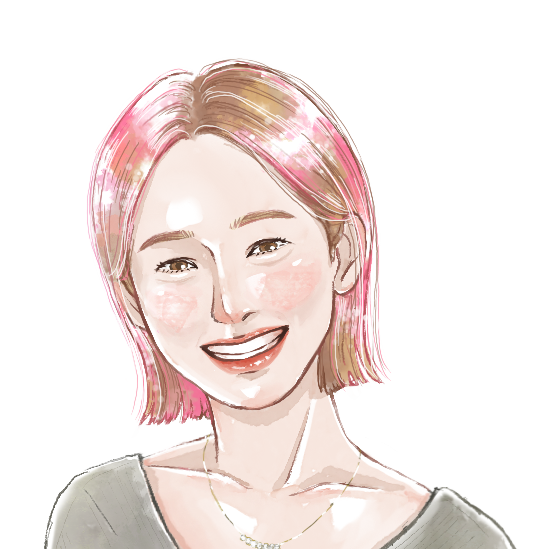
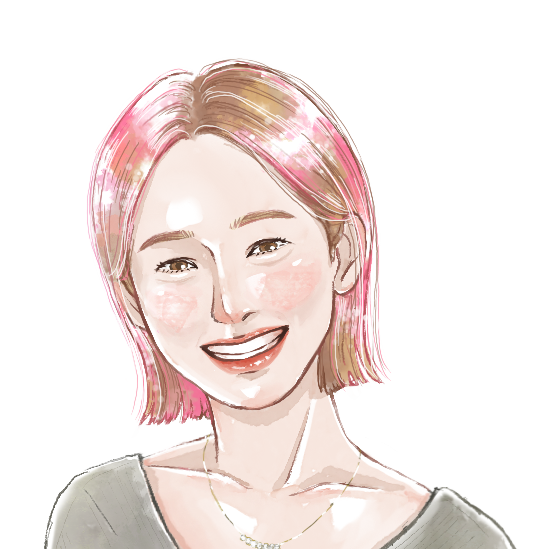
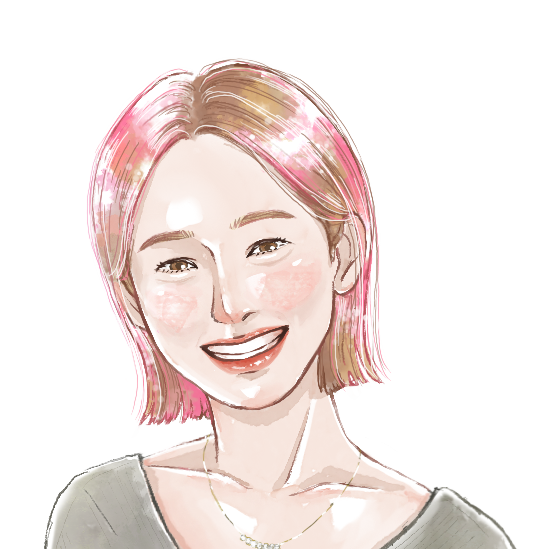
むしろ、保育者と楽しそうに遊んでいました
最初は泣いていた子どもが、先生の訪問を心待ちにする姿を見て、「この環境に安心してくれているんだな」と実感できました。
【まとめ】居宅保育を利用して感じたこと
・ 居宅保育は 「保育園の先生が自宅で保育をしてくれる」イメージ。
・ 保育内容は認可保育園と同じく「保育所保育指針」に沿った内容
・「我が子だけの先生」がいるので、安心して任せられるのが何よりの魅力
・ 家族以外の人が家にいることは我が家は特に気にならなかった
・ 利用を検討する際は家庭ごとの価値観や感覚を大切にし、無理のない選択をすることが重要

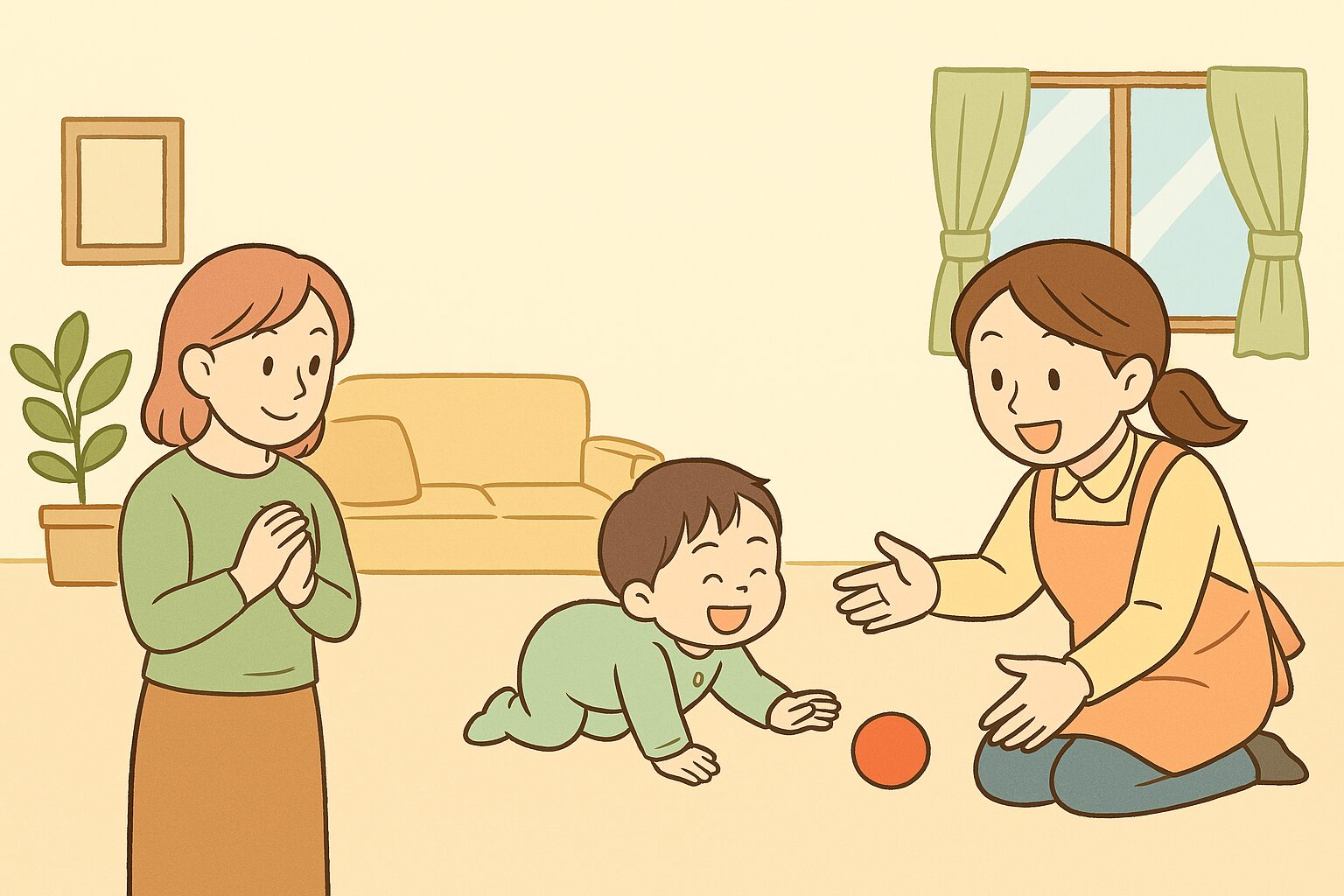
コメント